
「将来のことが少し心配…」と感じていらっしゃる皆様へ。
複雑な手続きや契約内容について、分かりやすく丁寧にご説明いたします。
ご本人様の意思を尊重し、安心して任意後見制度をご活用いただけるよう、
(公社)コスモス成年後見サポートセンター会員の行政書士が
誠心誠意サポートいたします。
まずは、あなたの想いをお聞かせください。
任意成年後見制度ってなに?
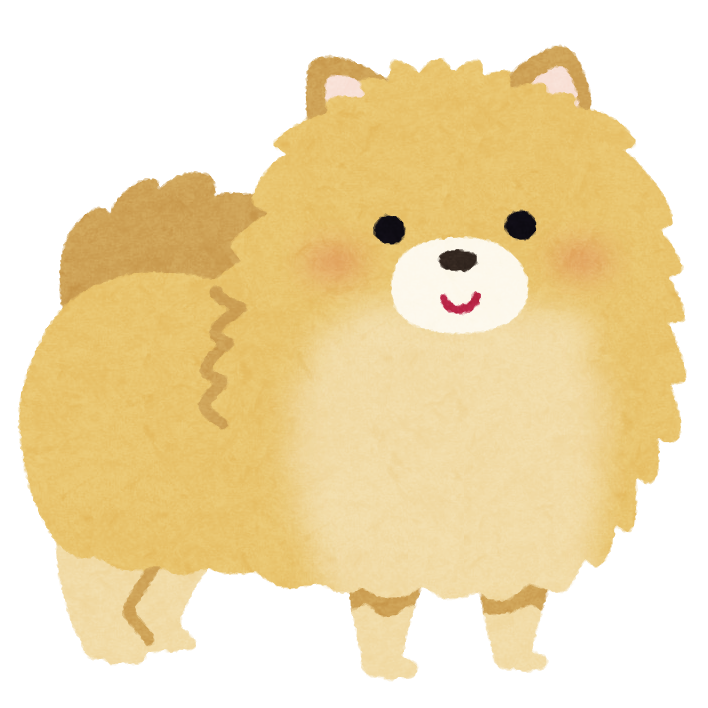
生きている間の対策です!



遺言は、亡くなった後の
対策だね。
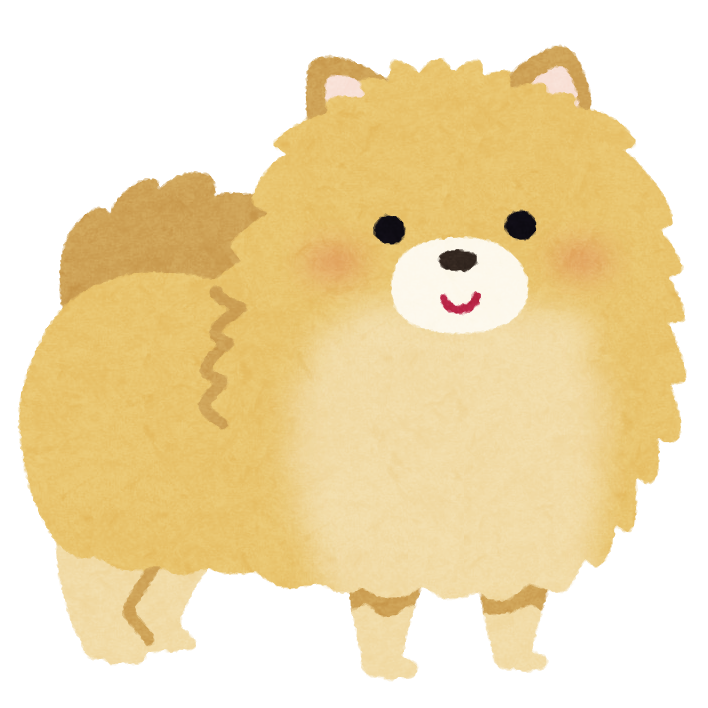
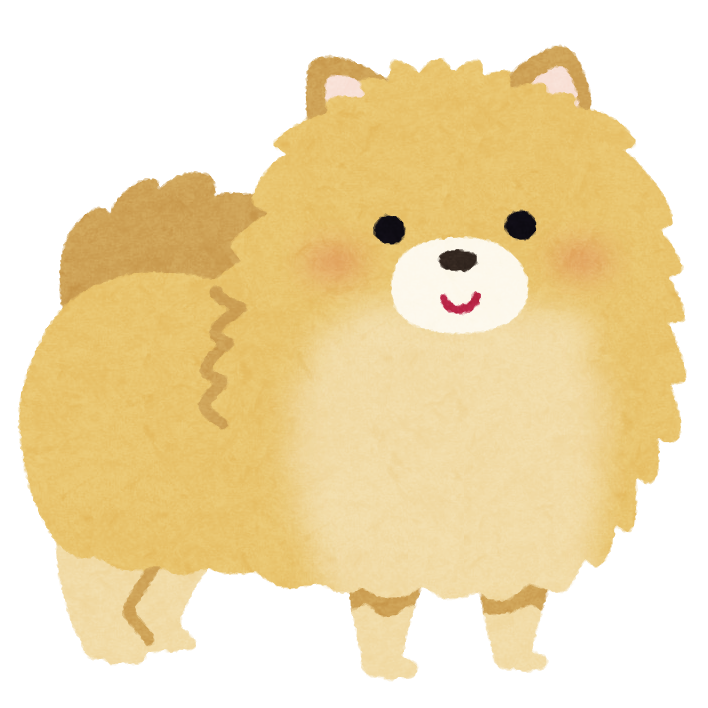
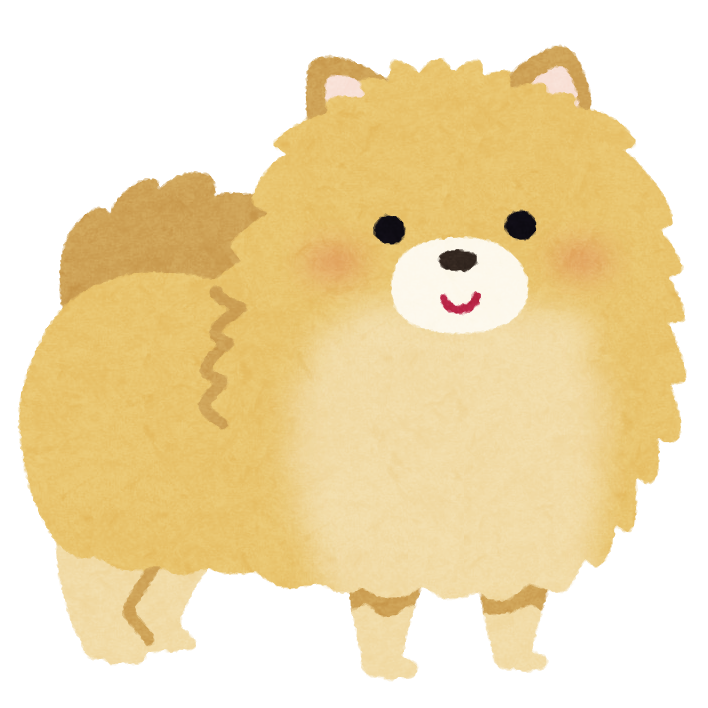
生きてる間のあれこれは、
信頼できる人に、
お任せしたいよね!



認知症になる前なら、
お任せする人を
選任してもらえるかも!
ひとりで決めることに不安のある方々を、
法的に保護し、支援する、詐欺の被害からお守りするのが
成年後見制度です。
任意成年後見制度では、ご自身で選んだ信頼できる人、
例えばご家族を「任意後見人」として申請することができ、
実際、裁判所で、その方が選任されることが多いようです。
例えば
- 認知症になって、ひとりで決めることがむずかしくなる前に
- 財産管理(不動産や預貯金などの管理、
遺産分割協議などの相続手続など)が
むずかしくなる前に
- 身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や
施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認
または解約など)などの法律行為をひとりで行うのが
むずかしくなる前に
- 自分に不利益な契約であることが
よくわからないままに契約を結んでしまい、
悪質商法の被害にあわないように。
任意後見人には、取消権はありません 法定後見人には取消権があります。


ステップ1
ご本人が、判断能力が十分なうちに、
将来、判断能力が低下した場合に備えて、
「任意後見人」になってほしい方との間で、
あらかじめ「任意後見契約」(公正証書)を締結しておき、
ステップ2
ご本人の判断能力が実際に低下した段階で、
ご本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者
(ご本人と任意後見契約を締結した、任意後見人になる予定の者)が、
家庭裁判所に対し、任意後見監督人選任の審判の申立てを行い、
家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任することにより、
任意後見契約が発効し、任意後見が開始します。
- 任意成年後見締結時に、例えば、あらかじめ内容を定めておけば、
- 不動産の売却
- 施設入居のための契約代行
- 定期預金の解約
- お孫さんに、入学祝をあげる
といったような契約はできますが、
任意後見監督人を通じて、
家庭裁判所の許可が必要になる可能性が高いです。
)
申立てをすると、裁判所の許可を得なければ
取り下げることはできません!
・ 配偶者
・ 4親等内の親族
1)親、祖父母、子、孫、ひ孫
2)兄弟姉妹、おい、めい
3)おじ・おば、いとこ
4)配偶者の親、子、兄弟姉妹
・ など、判断力のある成人ならだれでも
認知症になってしまう前に!


公証役場で公証人が作成した「任意後見契約公正証書」の
正本の交付を受け、
法務局で任意後見契約の登記をしておきます。
- あらかじめ、本人のために
委任する人、委任する事務の内容を定めます。
- 本人の生活
- 身上看護(施設入居のための契約とか)
- 財産管理
- 公証役場にて、公証人が「任意後見契約公正証書」を作成
- ご本人と、任意後見受任者は、その公正証書に署名+押印
- ⇒任意後見契約の締結
- ⇒任意後見契約の締結
- 「任意後見契約公正証書」の正本の交付⇒大事に保管!
- 公証人の嘱託により、任意後見契約の登記がなされます
- ⇒任意後見契約が有効に成立したことの登記
- ⇒これにより将来の任意後見に備える
まずはこれで、事象発生まで、普段通りの生活です。
これはあくまで「契約が存在する」という登記であり、
まだ任意後見人に権限はありません。
その後、現実に、ご本人の事理弁識能力が不十分になってしまったら


- 主治医に、「診断書(成年後見用)」を作成してもらいます。
- 家庭裁判所に対し、「任意後見監督人の選任の申立て」を
行います。(郵送でも持参でも) - 2週間の即時抗告期間(不服申し立てすることができます)
- 家庭裁判所の嘱託により、後見監督人が選任され、
- 法務局で任意後見開始の登記がなされます。
・ご本人を守るための制度なので、
資産運用は基本認められないようです。
例えば、賃貸アパートの運用、株式の運用等
・また、あらかじめ定めていなかった内容に関しては、
裁判所に申し出なければなりません。
例えば、お孫さんへの入学祝をあげたいとき等
「生前事務委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」を同時に締結
後見登記だけして、「任意後見契約」だけした後、
放置状態になるリスクが!
「生前事務委任契約」「死後事務委任契約」を、「任意後見契約」と
同時に締結する「移行型」が最も活用されています。
任意後見受任者が、任意後見開始前に、ご本人をサポートする契約
- 生活や療養看護に関すること
- 介護サービスの利用契約
- 医療(入退院)契約
- 福祉サービスの利用契約 など
- 財産管理に関すること
- 現金、預貯金通帳、証券などの管理
- 各種支払い
- 不動産の管理 など
ご本人が亡くなって、「任意後見契約」が終了後、
「死後事務委任契約」も締結しておくことで
ご自身の意思に沿ったサポートを、
人生の最期まで、そしてその後まで安心して託すことができます。
ご本人が、受任者に、自己の死後の事務を生前に依頼する契約
ご家族が亡くなった後、必要な事務手続きを行うのは大変なことです。
おひとり様、ご家族の負担を減らしたい方は、
家族以外の人に死後事務を任せることができます。
- 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
- 遺体の引き取り、散骨に関する手続きなど
- 永代供養に関する事務
- 医療費の支払い
- 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の
受領に関する事務 - 戸籍や年金などに関する行政官庁等への諸届け
- 公共サービスの解約手続き
- 親族、友人、知人への連絡
- 賃貸物件の解約
- 携帯電話やインターネットの解約
- 家財の処分 など


報酬
| 内容 | 報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 生前事務委任報酬 | ¥33,000~/月 | 内容により 別途追加料金 |
| 死後事務の委任契約書作成 | ¥66,000~ | 内容により 別途追加料金 |
| 移行型成年後見契約書作成 | ¥165,000~ | 内容により 別途追加料金 |
| 死後事務委任報酬 | ¥500,000~ | 応相談 |
| 任意後見報酬 | ¥33,000~/月 | 応相談 |